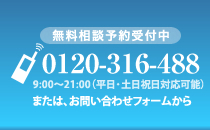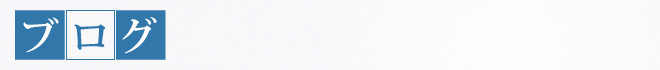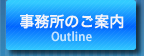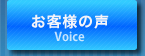2022.01.15
障害を持った子供がおられる親御様から「私がいなくなった後、生活していけるか心配です。」とご相談を頂きました。
これは昨今「親なき後問題」と言われています。「親なき後問題」とは、知的障害、精神障害などの障害を持つ子どもがいる家庭で、今のところは親が身の回りのことやお金の管理をしているから支障はないけれど、親がいなくなった後に子どもの生活が立ち行かなくなる問題です。
各家庭の事情によりますが、何も対策をしていなかったばかりに、親がいなくなってから、子どもの生活状況が一転してしまう事例が散見されます。
障害の内容、家庭の状況は十人十色なので、親なき後対策の具体的内容も人それぞれですが、まず大事なのは、子どもを福祉サービスにつなげ、サービスを拒否することがないようにしておくことです。
というのも、親なき後は子どもを助ける手立てとして障害者福祉や介護保険制度の利用が鍵になることがありますが、子どもがいざというときに福祉サービスの利用を拒んでしまうと、子どもが孤立し、危険な状況におかれるからです。
そして、親なき後は、お金の管理をどうするかという問題も重要です。例えば、金銭管理が苦手な方の場合、親なき後、一気にお金を使ってしまうといった問題が生じることがあります。
そういった問題を防ぐための方法には、あらかじめ子どものために「後見人」をつけておくという方法があります。
「後見人」とは、判断能力が不十分な人にかわり、本人の生活に配慮をしながら財産管理や事務処理をする人で、本人の4親等内の親族等がその選任を家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
「後見人」は、本人の判断能力に応じ、後見、保佐、補助といった名称の職務、権限が与えられ、その範囲で活動します。そして、基本的に終生続きます。
「親なき後問題」を考える方は、一度後見制度を検討してみてはいかがでしょうか。
また、場合によっては、信託や遺言という制度を併せて検討してみることも有益です。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.12.14
奨学金の返済が遅れていることについて相談を頂きました。
今、大学生の2人に1人は奨学金を利用しています。ほとんどの先進国では、奨学金は給付されるもので返済の必要はないのですが、日本の奨学金は「貸与型」のものが多く、それは本人が背負っていく「借金」を意味します。最近では、所得の減少や雇用形態の変化により、学生時代に借りた奨学金の返済が滞り、残元金と利息のほか、膨らんだ延滞金(約束の返還期日までに返還されないと課される利息)を含めて一括返還を求められるケースが急増しています。
延滞が長期間続いている場合には、奨学金の借入先は、裁判所の支払督促などの法的措置をとってくる可能性があります。支払督促とは、債権者(奨学金の借入先)の一方的な申立てにより裁判から発令されるもので、支払督促を受け取ったまま何もせずに放置しておくと、通常の裁判と同様、債権者の言い分だけが裁判所に認められ、最終的には給与や預貯金の差押えがされる恐れが生じてしまいます。
また、次のような独自の救済制度を採用している奨学金制度もあります。現在延滞中であっても、その理由が低所得や病気など、一定の返済できない事情によるときは、その証明書と願い出を提出して、返済を一時停止(猶予)してもらう制度(その間は、利息も延滞金も発生しない)や、一回あたりの割賦金(奨学金の分割返済金)の額を減らして返還期間を延長する減額返還制度等です。猶予制度の利用により、利息や延滞金が減額・解消したり、割賦金の減額返還制度の利用により、分割返済ができる額にまで縮減されることもあります。
支払総額が膨大で完済の目途が立たない場合には、生活再建のため破産・個人再生などの法的整理を検討した方が良いケースもありますが、親や親戚が保証人になっている場合には、仮にあなたが裁判所に破産の申立てをして免責(借金の支払義務がなくなること)を得られたとしても、保証人の債務(奨学金を返さなければいけない義務)は解消されないので注意が必要です。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.11.16
相続の相談の際によく頂く質問として「葬儀代は誰が負担するのか?」があります。
結論から言うと、一般的に、葬儀費用は、喪主(祭祀主催者)が負担することになります。
意外に思われるかもしれませんが、
葬儀の費用(死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用)を誰がどのように負担するかについては、
民法その他の法律において特に定められているわけではなく、
個別に、判例や慣習、相続人当事者の意向等を考慮しながら、
誰が負担するのが適当かを判断することになります。
予め葬儀に関する契約を締結していない場合、
相続人等関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合ですので、
追悼儀式に係る費用(葬儀)は、
自己の責任と計算において同儀式を準備し、
手配等して挙行した喪主が負担し、
埋葬等の費用については祭祀承継者(いわゆる「墓守」)が負担する、
という「喪主負担説」が採用されることになると思われます。
葬儀には、出費もありますが、
反面、香典料等収入もあるため、
喪主の判断(計算)で適当と思われる内容の式を挙げるものがやはり一般的となります。
各自の法定相続分(各2分の1)に応じて葬儀費用を負担することにし、
精算するのが、現実的にみて適当な合意内容かもしれません。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.10.08
最近よく頂戴するご相談です。
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者が承継することです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。一般的に相続の対象となる財産は1.現金や預貯金、株式等の有価証券、2.車・貴金属等の動産、3.土地・建物等の不動産、4.借入金等の債務が挙げられます。
3番の土地・建物等の不動産を相続により被相続人から承継したものの、不動産の名義変更を長期間行っていない場合、次のような問題が生じることがあります。
①相続人が認知症を発症し意思表示ができなくなると遺産分割の話し合いが困難となり、場合によってはそのために成年後見人を選任しなければいけない場合が生じることがあります。
②相続開始時点では名義変更に同意してくれていたとしても、時間が経てば相続人の気が変わってしまい、遺産分割の合意が困難になって相続登記が行えなくなることがあります。
③被相続人死亡当時の相続人が亡くなってしまい、別の人に相続権が移り協議が難しくなることがあります。特に血筋のない相続人の配偶者に相続権が生じてしまい遺産分割の話し合いができなくなることがあります。
では、相続による不動産の名義変更に期限や義務があるかというと現在のところはありません。このことは、相続税の申告であれば10カ月以内や相続放棄等の3カ月以内とは異なります。
しかし令和3(2021)年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が可決成立しました。この改正により不動産の登記名義人が亡くなったときは、当該相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記等をしなければならないこととされました。この義務に違反し、相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。この法律は公布の日である令和3年4月28日から3年以内に施行される予定ですのでいますぐということではありませんが、上記①、②、③の問題もありますので、相続登記手続を早めに行うことをお勧めします。
詳しくは、是非ご相談下さい。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.09.08
任意後見のご相談を頂き、先日公証役場にて契約に立ち会ってきました。
今回は私が後見人ではなくご長男様が後見人となる契約でした。
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が衰えた場合に備え、予め後見を頼む人を決めておく契約を結ぶことを言います。
何もしないで認知症になってしまった場合は、ご本人の意思が反映されず、ご家族以外の司法書士や弁護士といった専門職が後見人になる法定後見制度しか対策がありません。
ご自身が信頼できる方にお願いしたいという方は事前に契約を結ぶ事で将来に対する安心感が得られる訳です。
さて、Aさんが、Bさんに将来後見をお願いしたいと思って契約を締結したとします。
現在Aさんには判断能力がまだあるので、まだ後見は開始しません。
契約を結んだBさんは、後見人になるまでの間は「任意後見受任者」として後見登記簿に載ります。
では、どのタイミングで、どのようにして後見が発動されるのでしょうか。自動的に後見が開始される訳ではないのです。
任意後見の発動=後見監督人が選任された時。これが任意後見が開始されるタイミングです。
そして、監督人の選任には、任意後見人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
ですので任意後見はそれだけ契約することはほとんどありません。
AさんとBさんが離れて暮らす場合は「見守り契約」や認知症になる前から財産の管理を依頼する「財産管理契約」など、継続して関係性を築いていく方々が大半です。
中にはお亡くなりになるまで任意後見を発動しない事もございますが、
これが1番よいケースなんでしょうね。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.08.18
現在、遺産整理と遺言執行を合わせて10件ほどのご依頼を頂いており、毎日どこかの金融機関へ赴いております。
各金融機関によってその手続きの方法が異なるので非常に時間がかかります。
遺産整理の基本的な流れは下記の通りとなります。
①公正証書遺言・自筆証書遺言の有無を調査
被相続人が遺言書の作成をしていた場合は遺言書の内容が優先されるため、公証役場で公正証書遺言の有無を調査します。
②相続人の調査(戸籍の収集)
被相続人の出生から死亡時までの戸籍を取得し相続人を確定します。
全ての戸籍が揃いましたら、以前ブログでも説明しました法定相続証明情報を作成します。
ご依頼されるケースは多いですが戸籍の収集に関しては相続人様自らでも結構です。
③遺産の調査と財産目録の作成
預貯金・有価証券・不動産、役所や施設からの還付金、保険等全ての遺産を調査し、遺産目録を作成します。
④遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
確定した相続人で、誰がどの遺産を取得するかを決定し遺産分割協議書を作成します。
相続税の発生が予想される場合は、相続を専門とする税理士に関与して頂き、税務の要点を踏まえた内容で作成します。
⑤遺産の名義変更
・預貯金の解約または名義変更
・金融商品(※株、投資信託、債券等)の名義変更または解約
・不動産の名義変更(※売却のご相談も承っております)
⑥現金の分配・遺産の引渡し
司法書士名で遺産分割協議書の内容に従い相続人名義の預金口座にお振込み致します。
成果品(権利証・相続関係書類・金融商品等)と資料一式を引渡して遺産整理終了となります。
⑦相続税の申告・納付
相続税の申告・納付が必要な場合は、相続発生から10ヶ月以内に申告・納付します。
遺言執行の場合は①と④を省いてあとは同じ流れとなります。
早い案件で2ヵ月、遅い案件ですと1年ぐらいかかる事もございます。
経験された事のある方ならお分かりかと思いますが、戸籍の取得から各名義変更までご自身で行うとなると大変な労力と時間を要します。
基本的に手続きは全て平日に行う必要がありますので仕事をしながらとなると更に大変です。
ですが、それ以上に司法書士が間に入る相続手続きの代行業務の大きなメリットは、親族の争いになってしまう相続、いわゆる「争族」の抑止力の効果があります。
銀行預金などの払い戻し手続きは、相続人全員が合意して代表相続人を1人選び、その一人に亡くなった方の預金口座の名義変更したり、その一人に対して全額の払い戻しを行うことが多くあります。その後、代表相続人から他の相続人へ振込など行なって相続手続きをするということになります。
しかし、代表相続人が得たお金が何らかの使途で使われてしまったり、分配そのものが行われないケースも、残念ながらないとは言えません。代表相続人がお金を使い切ってしまって、解決できないということも少なくありません。
当事務所へ遺産整理・配当のご依頼を頂ければ、全相続人の代理人として銀行預金などの払い戻し手続きを行います。その後、各相続人に、法定相続分または相続人が合意した割合で振込を実行します。予め分配を行いますので、上記のようなトラブルが起きる心配はありません。
「相続」を「争族」にしないためにも、司法書士を間に挟むことをおすすめします。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.07.30
さて、遅くなりましたが前回の続きです。
法務局からの連絡は、抵当権者からの委任状に実印での押印及び印鑑証明書を添付せよとの事でした。
事前通知での登記の際には根抵当権者の登記済証・登記識別情報は再発行できないので、変わりに印鑑証明書と実印の押印された委任状が必要になります。
司法書士には何てことないですが、
登記申請書を作成したこの行政書士にそこまでの知識がなかったのは仕方無い事です。
ならばと、所有者様は抵当権者へ実印の押印と印鑑証明書を求めましたところ、
少々気難しかった抵当権者は「そんなことは聞いてない。」と協力要請を一蹴されました。
元々、えらく高金利な上、やれ交通費ややれ協力費やらと金銭を請求されていたようです。
ここで司法書士へ相談されたら別の方法へ移行することが可能でしたが、
ずるずると交渉し続けている中で、なんと抵当権者が体調を崩してお亡くなりになられました。
そうなると今度は抵当権者の相続人に登記申請をお願いせねばなりません。
相続人が多岐に渡り海外在住や行方が分からない方もいるようでここで当方に相談にお見えになられた次第です。
やはり、餅は餅屋です。
有難い事に当事務所にはホームページを見られた方々より多くのご相談を頂いておりますが、
自身の専門でない分野は当然ですが、
ある程度は出来そうかなといった案件でも、
信頼できる専門家を紹介させて頂いております。
それがお互いの為かと思います。
半端な知識での対応は危険を招く。
再認識させられる案件でした。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.07.08
先日、「個人が抵当権者である抵当権の抹消登記をお願いしたいのです。」とのご相談を頂きました。
早速ご来所頂きお話を伺ったところ、
実は自分で登記しようと試みたが結局出来なかったとの事で、
登記申請の取下げ後の書類も一緒にお持ち頂いておりました。
書類を確認するとどうもひっかかる。
「これはご自身で作成されたものですか?」と尋ねたところ、
元々は知り合いの行政書士に相談しており、
書類だけ作ってあげると言われハンコを押しただけとの事でした。
もちろん有料です。
これは「非司行為」といって、司法書士でない者が司法書士業務を行うことを言い、
立派な犯罪であり違法行為です。
行政書士は会社の議事録や定款の作成はその業務の一つですので、
会社設立や役員変更などその延長線上の商業登記の非司行為はあると聞いておりましたが、
抵当権の抹消登記などおそらく何らの経験も無い分野までタッチしている方がいるとは驚きました。
しかし、それが言いたいのではありません。
抵当権を抹消するには抵当権の設定登記をした際の「登記済証(登記識別情報)」と呼ばれる書類が必要です。
自宅を購入した際には「登記済権利証」と呼ばれる書類が交付されますが、
こちらは聞いた事がある方は多いと思います。
内容は同じで、自身が「所有者だ。」「抵当権者だ。」「地上権者だ。」といったことを証明するものです。
このケースはこの登記済証が無かったのですね。
この場合は「事前通知」もしくは司法書士か弁護士による「本人確認情報」が必要になります。
・事前通知とは、登記済証が提供されないで申請手続きがなされたとき、その登記が登記名義人本人の意思に基づいて申請されたのかを確認するため、法務局から登記済証を提供すべきであった登記義務者に「こういう内容の登記が申請されているが間違いないか。」という旨の通知が届きます。それに実印を押印して送り返すことによって手続きが進行するというものです。
登記官側で確認したうえで登記手続きを実行するための制度です。
・本人確認情報とは、登記申請をする際に登記済証を提出できない場合、資格者代理人(司法書士、弁護士)によって提供される申請人が登記申請権限のある登記名義人であることを確認できる事項が記載されている情報(書面)のことです。
このケースでは書類を作成しているのは行政書士です。
本人確認情報は作成できないので必然的に事前通知が選択されます。
登記申請書は通常の抵当権抹消と同じですので、
書籍を参考に申請書を作成し登記申請したのだと思います。
登記申請後、法務局から補正(登記申請に不備がある)連絡がありました。
何故でしょう。
少し長くなりましたので続きは次回に。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.06.25
Aさんから「夫が亡くなり、ご自宅の相続手続きを依頼したい。」とのご相談を頂きました。
Aさん夫婦には子どもがいないので、「相続人は、Aさんとご主人様の弟様となりますね。」とお話しすると、「私だけかと思っていました。」と驚かれておりました。
実はAさんのように「子どもがいないので、配偶者が亡くなった場合には、その財産は自分が全部相続できるはず。」とお考えになられている方は意外と多いのです。
しかし、配偶者の親・兄弟姉妹も相続人となるため、それらの方と財産を分ける形になってしまいます。
本ケースでは理解のある弟様でしたので、遺産分割協議を行いAさんが全財産を相続する事ができましたが、以前1度同様のケースで相続分を主張された事がありました。
以前より仲が悪かった兄弟間で弟が年老いた義理姉に自身の相続分を主張してきたのです。
また、最悪な事にそのケースでは相続財産は不動産しかなく、持分に応じた金銭を弟に支払うため、住み慣れた不動産を売却しなければなりませんでした。
ただ、今ではこういった事を防ぐため、「配偶者居住権」という制度があります。
(配偶者居住権とは、建物所有者である配偶者の死亡時において、その建物に住んでいるもう一方の配偶者の居住権(自宅に住み続けることができる権利)を保護するための制度です。)
このように夫婦に子供のいない世帯は相続トラブルに遭遇しやすく、当事務所でも遺言があればというケースは多くございました。
普段から、義理の両親や義理の兄弟姉妹と良好な関係を保っている場合には、そこまでトラブルに発展するケースは少ないのですが、関係が疎遠であったりすると、義理の両親や兄弟姉妹との間に本来立つべき配偶者が不在のこともあり、トラブルにつながるケースも多く見られます。
そこで残された配偶者が安心して相続できるための対策は何かというと「遺言」です。上記のようなトラブルは、そもそも義理の両親や兄弟姉妹と相続財産を分けることから発生しています。ですので、それを回避するために、「私の財産は全て妻(夫)に相続させる」といった内容の遺言をそれぞれが作成しておけば、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
そしてその際は、夫婦が共に死亡した場合の財産の遺贈先も記載する事をおすすめしています。
通常「死」は順番に訪れるものです。先に亡くなった方の遺言は有効で、残された配偶者へ財産は帰属しますが、残された配偶者の財産は死者に相続させることはできません。
自分たち二人が死んだ後は、どうでもいいというのであれば構いませんが、夫婦で築いた財産を特定の人や機関に引き継いでもらいたいのであれば、その内容を予備的遺言として、それぞれの遺言の中に記載しておく必要があります。
当事務所では日々、相続・遺言について相談を受けており、遺言に精通した司法書士が在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.06.10
事務所にご連絡頂いたAさんから「父の相続時に家族と関わりたくない。何年も会っていないので現在の生死は分からないが、仮に父が生存していたとして今の内に相続放棄をしたいのです。」と相談を頂きました。
何とも言えない事情ですが、残念ながら被相続人の生前に、相続放棄をすることは出来ませんし、仮に「私は要らないから」と相続人間で遺産分割協議したとしても法律上は無効となります。
相続放棄は、相続財産をいらないと考える人が自ら家庭裁判所へ申述をすることによって行うものである以上、生前に相続放棄を認めてもいいように思えます。
さらに、Aさんのように相続争いに巻き込まれたくないと考える人が事前に相続放棄をしておく実益もあります。
しかし、法律は生前の相続放棄を認めていません。それはなぜでしょうか。
理由の一つとして挙げられるのが、生前に相続放棄することを認めてしまうと相続財産を他の推定相続人へ渡したくないと考える人が、強迫や詐欺により相続放棄をさせてしまうことが考えられるからです。
また、借金まみれの状態だったが故相続放棄したが、その後資産の増加などで相続放棄を取りやめたいと考える人が出てきてしまうことも考えられます。
何より相続放棄はその字のごとく「相続が開始しないとできないもの」だからです。
では、生前の相続放棄に代わる手段はあるでしょうか?
①相続人の廃除
これは、一定の推定相続人(相続人になる予定の人)を相続人から廃除する、つまり、相続人ではないことにする手続きです。
被相続人の存命中にこの手続きを取ることができますが、その当該相続人による被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があったときに限られますので、実際には認められることは少ないようです。
②遺言+遺留分の放棄
遺留分については、家庭裁判所への申述の基生前の放棄が認められています。
遺留分とは、一定の推定相続人に保障されている最低限の相続分です。これは遺言でも排除する事は出来ません。
遺留分を生前に放棄し、また、遺言や遺贈、生前贈与を活用することで、被相続人の生前でも、遺留分を有している推定相続人に遺産を相続させないようにすることができるのです。
ただ、遺留分の放棄は相続放棄と違って本人の申述により取り消す事が可能ですので対策としては充分ではありません。
となると、生前に完全に相続権を放棄あるいは排除させる手続きはありません。
Aさんにもご説明の上、相続発生後に相続放棄をご依頼頂く約束をしてご了承頂きました。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉