いわゆる一人っ子の場合では、
父死亡後に母と子による遺産分割協議書が無ければ法定相続通りの2件の申請をしなければなりません。
登記研究という実務雑誌にそのような内容が掲載された後は、法務局でも実際そのような運用となっております。
遺産分割協議書とは文字通り2人以上で協議したもので、
権利が一人に帰属してしまった場合はその後協議はできず、
遺産共有関係を遡って解消することはできなくなるという理屈のようです。
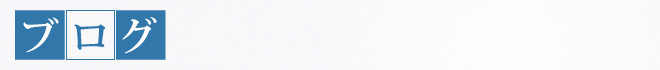
2023.11.25
2019年7月1日に施行された改正相続法により、「預貯金の仮払い」という制度が作られました。
今回は、この制度の内容を説明するとともに、活用方法についてもお話しいたします。
預貯金の仮払い制度とは、預貯金口座の相続に伴う出金手続を行う際、本来であれば法定相続人全員で行われる遺産分割協議に基づいて手続すべきところを、一部の相続人のみからでも出金手続が可能になる制度です。
預貯金の口座は、その名義人がお亡くなりになられた場合は凍結され、相続人全員の同意や遺産分割協議を経るまでは、入出金をすることはできなくなります。
しかし、葬儀費用等の支払いのためお亡くなりになられてから数日中に多額の現金での支払いが必要になるなどの不都合があったため、一定金額を限度として相続人の一人から被相続人名義の預貯金口座からの出金をできるようにしたことが、預貯金の仮払い制度の概要です。
では、実際にいくらまで出金できるのでしょうか。これは法律上決められており、次のABいずれか低い方の金額が上限となります。
A 死亡時点での預貯金残高×法定相続分(相続人の取り分)×3分の1
B 金150万円
具体的な事例に当てはめると、次のような計算式になります。
例1 預貯金残高 金300万円 相続人 子供二人(法定相続分は各々2分の1)
この場合には、次のように計算されるため金50万円が上限となります。
金300万円×(2分の1)×(3分の1)=金50万円 < 150万円
例2 預貯金残高 金1500万円 相続人 子供二人(法定相続分は各々2分の1)
この場合には、次のように計算されるため、例1とは異なり金150万円が上限となります。
金1500万円×(2分の1)×(3分の1)=金250万円 > 150万円
なお、預貯金口座が複数の金融機関に存在する場合には、この計算式は、各金融機関ごとに適用されることになりますので、複数の金融機関で手続をする場合、出金できる総額が金150万円を超える可能性もあります。また、仮払い制度を利用しても支出に対するお金が足りない場合、家庭裁判所で仮処分という別の手続を経ることで、法定相続分までの金額を出金できる可能性はあります。
仮払い手続の際に必要な書類関係についてですが、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等(出生時から死亡時までの一連のもの)や、手続をされる相続人の方の印鑑証明書等、いくつかの公的資料が必要となります。この必要書類は、各金融機関ごとにその取り扱いが異なりますので、お手続をされる金融機関に問い合わせいただいてから取得されることをお勧めいたします。
また、仮払い制度を利用する際に、いくつかの注意点もあります。他の相続人と相談せずに手続ができてしまうため、後々トラブルが生じてしまったり、多額の借金の存在に後日気づいたけれども、相続放棄ができなくなってしまうという可能性もあります。
預貯金の仮払い制度は、相続手続をする際に活用すればとても便利な制度ではありますが、その利点だけでなく欠点もありますので、実際に制度を活用する際には、ぜひ、ご相談いただいてから手続されることをお勧めいたします。
2023.09.27
大変お問い合わせを多く頂いております相続登記の義務化ですが、いよいよ令和6年4月1日からスタートされます。
長年にわたって相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、公共工事が進められなくなる、不動産の管理が行き届かなくなり周辺の環境が悪化するなどの問題が生じています。
そこで、法律を改正し、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得した(ことを知った)日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
また、相続人による話し合い(遺産分割協議)により不動産を取得した場合も、話し合いによる決定から3年以内に申請をする必要があります。
そして、正当な理由がないのに申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が未了であれば義務化の対象となりますので注意が必要です。
ただし、これらの不動産については、令和9年3月31日まで3年間の猶予期間が設けられています。
相続人の人数が多いなどの理由により、話し合いで相続の仕方がまとまらない場合は、裁判所で話し合いを行う制度(遺産分割調停)を利用するのも一つの方法です。
相続人のうち一人が申立人となって裁判所へ申し立てを行いますが、申立書の作成や必要書類の取得(戸籍謄本等)について、司法書士が相談に応じることができます。
話し合いがまとまらず、相続登記を行わないままにしておくと、対象となる相続人が増え、ますます解決が遠のく結果となってしまう可能性がありますので、なるべくお早めにご相談下さいませ。
2023.07.21
相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日にスタートしました。
「相続土地国庫帰属制度」は「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理の負担が大きい」などの理由により、相続をした土地を手放したいというニーズが高まっていることから創設されました。
遠方に所有する土地などで、利用を予定していない土地を相続した場合、管理ができないまま放置されるケースもあります。また、利用の予定がないからということで、相続登記をすることなく、登記簿からは直ちに所有者が判明しない「所有者不明土地」が発生することも想定されます。
国は、所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月から一定期間内に相続登記などの手続きを行うことを義務付ける「相続登記の義務化」を開始します。そして「相続登記の義務化」に先立って、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、国(国庫)に、土地を帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」をスタートしました。
「相続土地国庫帰属制度」は、買い手のつかない不動産を相続した方にとっては、待望の制度といえます。しかし、相続した土地を国庫に帰属させるにはさまざまな条件があるため、必ずしも国に引き取ってもらえるとは限りません。
土地だけを国庫に帰属させる制度ですので、建物が建っている場合には、あらかじめ、建物を解体しておく必要があります。相続の際に、土地が共有になっている場合には、共有者全員で手続きをすることが必要となります。さらに、公道に通じない土地は国庫に帰属することはできないなど、さまざまな条件が設けられています。
また、申請の際には、国庫に帰属させたい土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真を添付する必要があります。境界杭などがあって、境界が明らかな場合は良いのですが、一見してわからない場合には、隣地の所有者と確認して、境界杭を打つなどをすることが必要となります。
申し立てに当たっては、申請手数料が1筆1万4千円必要となります。国庫に帰属できることが承認された場合には、10年分の管理費用に相当する金額を負担金として納付することが必要となります。負担金の金額は、最低20万円となっており、土地の利用状況、面積、法令上の利用の制限などによって決まってきます。
国庫帰属を望むような土地、いわゆる山林等の値段がつかない土地が実際に適用となケースは少ないように感じますが、「相続登記」「相続土地国庫帰属制度に」ついてお聞きなりたい方は是非当事務所までご連絡下さいませ。
2023.02.09
遺言で、財産を相続できなかった兄弟から、遺留分を請求されたがどうすれば良いかとご相談を頂きました。
遺留分とは、相続人の最低取得分として保障されている遺産の一定割合のことです。これは、遺言の自由を制約しますが、遺言を完全に自由にしてしまうと、全財産を遺言で他人に譲ることも可能となるため、相続人の生活保障を図るために一定割合を留保すべきこととされたのです。
遺留分が認められるのは、配偶者、子、孫、直系尊属(父、母、祖父、祖母)が相続人になった場合で、兄弟姉妹、おい、めいは相続人になっても遺留分は認められません。
認められる遺留分の割合は、配偶者、子、孫については相続分の半分、直系尊属については3分の1で、同順位の相続人が複数いる場合は、さらにその頭割りになります。相続人が配偶者と子2人である場合、子ひとりの相続分は4分の1ですが、遺留分はさらにその半分の8分の1です。遺留分を請求するかどうかは各相続人の自由で、ある相続人が請求しなくても、他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
また、遺留分の算定の基礎となる財産は、被相続人の死亡時の財産だけでなく、1年以内に生前贈与(相続人に対して婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与は10年以内)された財産も含みます。被相続人と受贈者の双方が遺留分を侵害することを知っていた場合は、1年(相続人に対しては10年)以上前の贈与も含みます。死亡時の遺産総額が4千万円であったとしても、死亡前1年以内に2千万円の生前贈与をしていれば、先の例の子ひとりの遺留分は500万円ではなく、750万円になります。
遺留分を侵害された場合、補償を求めることができます。以前は、遺産全体に対して一定割合(例えば8分の1)を取得するものとされ、この共有持分を金銭で清算するかしないかは当事者の自由とされていたので、金銭的清算を拒まれたり、清算額が折り合わないなどで紛争となることが多くありました。
近時の民法改正により、遺留分の侵害額の補償は、最初から金銭による清算とされ、補償のための金銭がない場合、裁判所に期限を付けてもらうこともできるようになりました。数年程度の延べ払いが認められるようになったのです。弟から請求を受けた相談者は、これに応じる義務はありますが、即時の支払が困難であれば、分割払いや、交渉次第で特定の不動産等による代物弁済によることはできます。
2021.11.16
相続の相談の際によく頂く質問として「葬儀代は誰が負担するのか?」があります。
結論から言うと、一般的に、葬儀費用は、喪主(祭祀主催者)が負担することになります。
意外に思われるかもしれませんが、
葬儀の費用(死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用)を誰がどのように負担するかについては、
民法その他の法律において特に定められているわけではなく、
個別に、判例や慣習、相続人当事者の意向等を考慮しながら、
誰が負担するのが適当かを判断することになります。
予め葬儀に関する契約を締結していない場合、
相続人等関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合ですので、
追悼儀式に係る費用(葬儀)は、
自己の責任と計算において同儀式を準備し、
手配等して挙行した喪主が負担し、
埋葬等の費用については祭祀承継者(いわゆる「墓守」)が負担する、
という「喪主負担説」が採用されることになると思われます。
葬儀には、出費もありますが、
反面、香典料等収入もあるため、
喪主の判断(計算)で適当と思われる内容の式を挙げるものがやはり一般的となります。
各自の法定相続分(各2分の1)に応じて葬儀費用を負担することにし、
精算するのが、現実的にみて適当な合意内容かもしれません。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.10.08
最近よく頂戴するご相談です。
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者が承継することです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。一般的に相続の対象となる財産は1.現金や預貯金、株式等の有価証券、2.車・貴金属等の動産、3.土地・建物等の不動産、4.借入金等の債務が挙げられます。
3番の土地・建物等の不動産を相続により被相続人から承継したものの、不動産の名義変更を長期間行っていない場合、次のような問題が生じることがあります。
①相続人が認知症を発症し意思表示ができなくなると遺産分割の話し合いが困難となり、場合によってはそのために成年後見人を選任しなければいけない場合が生じることがあります。
②相続開始時点では名義変更に同意してくれていたとしても、時間が経てば相続人の気が変わってしまい、遺産分割の合意が困難になって相続登記が行えなくなることがあります。
③被相続人死亡当時の相続人が亡くなってしまい、別の人に相続権が移り協議が難しくなることがあります。特に血筋のない相続人の配偶者に相続権が生じてしまい遺産分割の話し合いができなくなることがあります。
では、相続による不動産の名義変更に期限や義務があるかというと現在のところはありません。このことは、相続税の申告であれば10カ月以内や相続放棄等の3カ月以内とは異なります。
しかし令和3(2021)年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が可決成立しました。この改正により不動産の登記名義人が亡くなったときは、当該相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記等をしなければならないこととされました。この義務に違反し、相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。この法律は公布の日である令和3年4月28日から3年以内に施行される予定ですのでいますぐということではありませんが、上記①、②、③の問題もありますので、相続登記手続を早めに行うことをお勧めします。
詳しくは、是非ご相談下さい。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.08.18
現在、遺産整理と遺言執行を合わせて10件ほどのご依頼を頂いており、毎日どこかの金融機関へ赴いております。
各金融機関によってその手続きの方法が異なるので非常に時間がかかります。
遺産整理の基本的な流れは下記の通りとなります。
①公正証書遺言・自筆証書遺言の有無を調査
被相続人が遺言書の作成をしていた場合は遺言書の内容が優先されるため、公証役場で公正証書遺言の有無を調査します。
②相続人の調査(戸籍の収集)
被相続人の出生から死亡時までの戸籍を取得し相続人を確定します。
全ての戸籍が揃いましたら、以前ブログでも説明しました法定相続証明情報を作成します。
ご依頼されるケースは多いですが戸籍の収集に関しては相続人様自らでも結構です。
③遺産の調査と財産目録の作成
預貯金・有価証券・不動産、役所や施設からの還付金、保険等全ての遺産を調査し、遺産目録を作成します。
④遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
確定した相続人で、誰がどの遺産を取得するかを決定し遺産分割協議書を作成します。
相続税の発生が予想される場合は、相続を専門とする税理士に関与して頂き、税務の要点を踏まえた内容で作成します。
⑤遺産の名義変更
・預貯金の解約または名義変更
・金融商品(※株、投資信託、債券等)の名義変更または解約
・不動産の名義変更(※売却のご相談も承っております)
⑥現金の分配・遺産の引渡し
司法書士名で遺産分割協議書の内容に従い相続人名義の預金口座にお振込み致します。
成果品(権利証・相続関係書類・金融商品等)と資料一式を引渡して遺産整理終了となります。
⑦相続税の申告・納付
相続税の申告・納付が必要な場合は、相続発生から10ヶ月以内に申告・納付します。
遺言執行の場合は①と④を省いてあとは同じ流れとなります。
早い案件で2ヵ月、遅い案件ですと1年ぐらいかかる事もございます。
経験された事のある方ならお分かりかと思いますが、戸籍の取得から各名義変更までご自身で行うとなると大変な労力と時間を要します。
基本的に手続きは全て平日に行う必要がありますので仕事をしながらとなると更に大変です。
ですが、それ以上に司法書士が間に入る相続手続きの代行業務の大きなメリットは、親族の争いになってしまう相続、いわゆる「争族」の抑止力の効果があります。
銀行預金などの払い戻し手続きは、相続人全員が合意して代表相続人を1人選び、その一人に亡くなった方の預金口座の名義変更したり、その一人に対して全額の払い戻しを行うことが多くあります。その後、代表相続人から他の相続人へ振込など行なって相続手続きをするということになります。
しかし、代表相続人が得たお金が何らかの使途で使われてしまったり、分配そのものが行われないケースも、残念ながらないとは言えません。代表相続人がお金を使い切ってしまって、解決できないということも少なくありません。
当事務所へ遺産整理・配当のご依頼を頂ければ、全相続人の代理人として銀行預金などの払い戻し手続きを行います。その後、各相続人に、法定相続分または相続人が合意した割合で振込を実行します。予め分配を行いますので、上記のようなトラブルが起きる心配はありません。
「相続」を「争族」にしないためにも、司法書士を間に挟むことをおすすめします。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.06.01
住んでいた家が長年空き家になったままの方よりご相談を頂きました。
市役所より空家に関する通知が届いた事がきっかけでした。
平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されております。
この法律により、空き家の所有者は、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家の適切な管理に努める」必要があると規定されました。
また、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ又は著しく衛生上有害となるおそれのある空き家については、市町村長から除却、修繕等の対応をするよう助言・指導が行われる場合があることになります。
ですので、相続人の方は空家が、「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」にならないよう管理する必要があります。
長年居住していなくても、適切な管理がなされており、建築物に著しい傾斜がみられ倒壊するおそれがある、ゴミの放置等周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼしている等のような状態でなければ、当該空き家について対応するよう助言・指導されることはないでしょう。
反対に上記に該当する場合は、所有者自身が何らかの対応をする必要があります。
空き家の除却については、市町村により費用の助成制度がある場合もありますので、当該空き家の立地する市町村にお問い合わせください。
なお、管理が不適切で、市町村からの助言・指導がなされ、状態が改善されず、市町村から勧告がなされた場合は、当該建築物の敷地についての固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなり、敷地に対する固定資産税の減額措置が受けられなくなります。
また、管理の一面として、早めの相続登記を行うことも検討されたほうがいいでしょう。
亡くなられた方の名義のままにしておくと、いざ処分等を行おうとする場合に、他の相続人の協力が得られない可能性があります。当該相続人も亡くなって数次相続が発生すると、相続登記を行うのに余計に時間も費用もかかることになります。
役所より通知が届いた場合は慌てずに、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.05.18
相続登記をご依頼いただく際、「物件は自宅のみです」と言われる場合が多いですが、実際には自宅以外にも不動産を持っているケースがあります。
特に多いのは、自宅の道路部分いわゆる「私道」です。
自宅の前の土地が私道の場合、たとえ所有者であってもそれはあくまで道路のため固定資産税上は「非課税」になり、自分の土地であると認識していないことがよくあります。
当然非課税のため、毎年春ごろに届く固定資産税の課税通知書にも記載されていないのです。
もしこの「非課税道路」に気づかずに自宅の相続登記を終えてしまうと、いざ売却することになった際に不都合が生じます。
自宅とその道路はセットですので、道路も合わせて買主に引き渡さなければならず、道路部分の相続登記を終えるまでは自宅を売る事ができないのです。
この場合困ってしまうのは再度遺産分割協議をすることになる事です。
相続人の数が少なければ簡単にやり直せるケースもありますが、相続人が多い場合や、相続人間で関係性が悪く、簡単に押印の貰い直しができないケースもあります。
更には年月が経過していて、押印を貰い直す前に相続人の一人が亡くなってしまったり、認知症になったり、海外へ居住しているとなると事態はさらに悪化します。
そのため、我々司法書士が相続登記を受任した際には「名寄帳」を取得します。
名寄帳とは、個人の方が所有している不動産の明細を一覧で確認できるもので、非課税の不動産も記載されます。
名寄帳は、所有者の名前に紐づく不動産が記載されているのですが、全国各地の所有状況がすべて確認できるわけではありません。
所在地を管轄する役所ごとに名寄帳は作成されており、管轄外の所在地については、そのエリアの名寄帳を別途確認しなければなりません。
役所では、固定資産税を課税するための基本となる固定資産税課税標準額を決めるために、一筆(土地)一棟(家屋)ごとの不動産を現地調査して記録しています。
そのため、未登記でも、固定資産税が非課税となっている不動産でも、管轄内であればすべて記載されているので、相続財産を把握するのに役立ちます。
ですが名寄帳の中身は、自治体により非課税不動産の全てが記載されているかどうかが異なっていますので、絶対ではない事を注意しなくてはいけません。
当事務所では、名寄帳の他に権利証や、図面等で私道部分の有無を総合的に調査し、相続の対象物件を網羅するようにしています。
相続登記をする前段階のとても大切なプロセスとなります。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.05.10
当事務所では遺産整理業務のご依頼をよく頂きます。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様に代わり、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けする業務です。
司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
そしてこの時必ず作成するのが法定相続証明情報です。
相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関、保険、年金など多くの窓口で相続手続をとることになります。
その際、これまでは、亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍関係書類一式を各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。
平成29年5月29日に開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍関係書類一式とともに、相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が確認して誤りがなければ、一覧図の写しに認証文を付した証明書を、無料で、必要な通数を交付するという制度です。
各種の相続手続において,この証明書を戸籍関係書類一式の代わりとして提出することで、複数の手続を同時に進めることができ、何より先方の担当者による戸籍の読み取りの時間が無くなるので大幅な時間短縮につながります。
制度施行当社は一部の金融機関や役所では、情報不足のため取り扱えなかった事もありましたが今ではそのような事態はおこりません。
むしろ今ではネット証券口座の相続では法定相続証明情報を要する場合もございます。
税務署への税務申告にも使えますので税理士からご依頼いただくこともございます。
まだまだ利用実績は少ないようですが、この法定相続証明情報取得のみのご依頼も頂いておりますので、ご興味がある方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡下さいませ。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.04.12
父が亡くなり、特に相続手続きをしないまま数年後に母が亡くなり、
相続人が兄弟2名だけとなった状態での相続登記のご依頼を頂きました。
本来、相続が発生した場合にはその時の相続人間で遺産分割を行い相続登記までをしなければいけません。
しかし、こういったケースは意外にもとても多く、実務では「数次相続」と呼ばれております。
では、相続手続き上でどのように相続登記をすればいいのでしょうか。
今回、お父様が亡くなられて順にお母様が亡くなっております。
この場合、お父様を被相続人として考えると、
母が4分の2・兄弟4分の1ずつの相続権を持っており、
母がその4分の2の相続権を持ったまま死亡したということは、
結果として兄弟二人が父の相続分を半々で取得したことになります。
では、単純に父の相続財産をそのまま二人が法定相続で取得することができるように思えますが、
相続登記手続き上は、その不動産を誰がどのような原因でどういった順で取得したのかを明示する必要があります。
原理原則では、父が死亡したことにより母4分の2、兄弟が各4分の1の登記を申請した後に、
母の4分の2の持分について兄弟で協議し名義を変更する形となります。
しかし、そのような方法を取ると相続登記に関する費用(登録免許税等)が余計にかかってしまうことになります。
こういったケースの場合、父母の相続をまとめて遺産分割してしまう方法を使います。
具体的には、一通の遺産分割協議書の中に父母の相続について記載する、
つまり、兄弟は「父親の相続人であると同時に、父親の相続人であった母親の相続人」という立場で遺産分割する事になります。
これであれば、直接父から兄弟へ名義変更することが可能ですし費用も手間もかからなくて済みます
ただし、これはあくまで兄弟で協議出来たから可能な方法となります。
いわゆる一人っ子の場合では、
父死亡後に母と子による遺産分割協議書が無ければ法定相続通りの2件の申請をしなければなりません。
登記研究という実務雑誌にそのような内容が掲載された後は、法務局でも実際そのような運用となっております。
遺産分割協議書とは文字通り2人以上で協議したもので、
権利が一人に帰属してしまった場合はその後協議はできず、
遺産共有関係を遡って解消することはできなくなるという理屈のようです。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.03.22
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届きましたが、
「これは一体何でしょうか?」とのご相談を頂きました。
法務局は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
という舌を噛みそうな法律に基づいて調査を行い、
土地の所有者が亡くなっているけれども、
その後も長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明した土地について、
土地の所有者の法定相続人に対して相続登記をしてもらうために、
「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
「長期間相続登記等がなされていないことの通知」が届いた場合、
対象土地の相続人の一人になっているというわけです。
この法務局による相続人の調査に私も関わっております。
いつもとやり方が違う上に、
期限など法務局にあれこれ指示されるので非常に面倒でした。
通知を受け取り相続登記手続きを検討される場合は、
土地を管轄する法務局で、
土地の登記事項証明書と、
被相続人の法定相続人の一覧図(法定相続人情報)を取得してください。
相続登記をする場合に必要となる戸籍一式が原則不要となり、
正直この点はかなりラッキーです。
ただ、あくまで相続人の確定までですので、
法定相続人が複数いる場合は、
対象土地を法定相続人間で誰がどのように相続するのか、
話し合っていただく遺産分割協議等が必要となります。
ご自身での手続きが難しいと感じた場合は、
相続登記の専門家である当事務所にご相談ください。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉
2021.03.08
相続登記に関する大きな改正がなされそうです。
その内容は相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すというものです。
また、住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、
2年以内に申請しなければ5万円以下の過料とするようです。
現在はなぜだか相続が発生しても相続登記は義務ではありません。
申請しなくても罰則はありませんので、
土地そのものの価値が低かったり、
手続きが面倒だといった理由で放置される事は多いのです。
当事務所でもこれまで多くの相談を頂きました。
死亡者の名義のまま年月を経れば、それだけ相続人の数が増えてしまいます。
必然的に相続登記までの費用が嵩む→放置へと気持ちが流れる方は多くいらっしゃいました。
その結果、所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、
周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題があり、
公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースもありました。
その所有者不明地は九州全土の規模に及びます。
これらの解消が施行の目的でしょうが、ここに大きくメスを入れるようです。
国庫に戻したり、
共有物件でも管財人をおいて処分ができるようしたりと、
かなりの法改正がされるようですから、
これはもう司法書士として業務に密に繋がる改正です。
今後も注視していきたいと思います。
神戸・兵庫の「街」のホームロイヤー
司法書士 福嶋達哉